| 宮の入家住宅の地域的特性 | 民家の観かた2:主屋 |
| B.主屋 1.平面型の変遷 民家研究の主な対象時代は江戸時代中期以降である。理由はそれ以前建造の現存民家が少ないことで、江戸時代以前となると、現存数は急激に少なくなる。それらを見ると、上部構造の柱梁は非常に簡素で、それに加え水平耐力を堀立柱に頼っていたため、百年単位での耐久性に乏しかったのであろう。(この頃まで、竪穴住居以来の堀立柱の伝統を保っていた) それが江戸時代中期以降に建造された民家は、見違えるほどに重厚な構造になる。これは江戸中期に社会が安定し、幕府も農業の生産性改良に力を注ぎ、農業経営が豊かになった背景があるからであろう。現在でも好まれるデザインの住宅が発表されると、多くの家がその形で作られる。また作業場併用住宅では扱い商品を変えると使い易い形に改修をする。江戸時代の農家も200年以上の時間を掛け、ゆっくりではあったが、より新しい型へと進化した。特に貨幣経済の発達と共に生産物が変化し、家の形も大きく変わていった。 この地域に現存する古い型は、四つ間型以前に遡る。民家は原初的には土間と寝床だけの一間取りから始まる。次に土足でない生活スペース(広間・座敷・勝手などの用途室)1室が付いた二間型、此処までは自家用の生産・生活スペースに関して進化する。三間以上の部屋数になって初めて接客空間が生まれる。接客空間が様々な形に展開して四ツ間型に至るが、その後の六ツ間型以降は養蚕飼育場として展開する。この地域での一間・二間はかなり古く、又小さいことから建替えられてしまう率が高く、資料のある民家は、三間型あたりから始まる。これらの多くは納戸あるいはヘヤという寝室専用室がある型である。前出の“藩政と民家”では『江戸時代に進化した平面部分は接客スペースである』と言っている。その時代までに形成された土間〜広間(座敷)〜納戸という生産と生活スペースに加えて、デイ・奥の間という接客スペースが江戸中後期になって加えられた。そして、農民が豊かになるにつれ、広間型から、喰違四間、四間、整形四間、六つ間(名主階級の名主型六つ間はもっと前に出現)へと進化した。構造が頑強になった民家は、これら全ての型が改修され現在でも使われている例が多い。 2.旧宮鍋家の主屋 武蔵村山市、岸に新築した宮ノ入家住宅は、狭山丘陵の東端、東大和市高木に昭和60年まで建っていた旧宮鍋家住宅を手本に新築復元したものである。出典資料は東大和市教育委員会発行の『旧宮鍋作造家住宅解体調査報告書』とその関係資料で、その資料を基に関係各位了解の上、復元したものである。里山体験の利用施設であるので、整備として、一部の平面を単純化したが、柱の太さ、梁の組み方・長さなど可能な限り実物の寸法を踏襲している。旧宮鍋家住宅は調査と同時に解体され現存しない。 この家の解体時の姿はA図の通りである。200年以上使われたが、その間、何回もの模様替えが行われた。文化財としての記録を残し建築当初の形を確定する為、解体と共に痕跡調査が行われた。 遡り調査によれば、建築当初はE図の通り、喰い違い四つ間型であった。この形に寝室専用の納戸(あるいはヘヤ)がない。デイに押入れが付いているので、ここが寝室兼用になっていたのであろう。1間巾で喰い違っているので広間から引違い戸で奥の間と繋がっているが、生活部分と接客部分が不連続で×型配置になっている。デイの寝室スペースが補助的な場合は、その様な例はある。E図ではカッテを二つに分ける建具が置き戸棚右側に入っていたかも知れないと分析しているので、3帖弱の広さであるが、置き戸棚裏が主寝室であった可能性はある。あるいは奥の間の入口がデイの南側でなく奥の間の西側であったのかもしれない。または、カッテ上の中2階が主寝室であったとの言い伝えがあるので、×型配置は使い辛いので、そのような使い方を実際にしたのかもしれない。 旧宮鍋家住宅の建築時期は、調査報告書によると江戸中期末と推測している。棟札や建築に関する書付けは無かったが、言伝えや間取り、構造から類推してのことである(類推とは書付や実証される資料がある建物との比較でである) 旧宮鍋家住宅は当敷地近く、狭山丘陵山麓の自然村にあることから、歴史的、風土的にも同一背景であると認め、宮の入家住宅の形式として採用し、旧宮鍋家建築当初の姿を復元している。 3.民家の床仕上 旧宮鍋家住宅は喰違い四間(クイチガイヨツマ)とう形式であるが、それ以前はどうなっていただろうか。 江戸時代になると、ほぼ現存する民家形になったが、それ以前は家中が土間で、いわゆる土座であった。土座というのは地ベタに直に暮らすことで、板の間や、畳の間のように、土から離れた生活をしていないことである。構造は、地面の上にモミガラ、またはワラ、茅などを敷き詰め、その上にムシロをしいた。寝床はさらに藁を敷いて寝ていたようだが、床が乾燥さえしていれば本当にあったかそうな構造で、実際、昭和の始め頃まで広範囲に残っていた様子が報告されている。上げ床構造が普及してきても、寒い地方では、なかなか無くならなかったそうである。上層農民の家も同様であったので造作費を小さくする為ではなかったようだ。民家の構成がかなり発展した段階でも生活の主要な場である座敷スペースが土座であった例は沢山ある。範囲は東北から九州まで日本全域に広がっていた。家中が土座であった時代は、多くが、掘建て柱の構造であった。今風の考え方では、『土座の一部に床が張られ、その周囲が壁や建具で仕切られて、部屋に昇格していく』と思ったが、そうではなく、土座のまま部屋の分離が進行し、幾つかの部屋から徐々に床張りをしていったらしい。間取りも、ひと間取り、ふた間取りへと発展していき、何部屋かに竹の簾の子や板張りが出現していった。床上室が出来て寝床がそちらに移っていったが、冬、寝るときは寒いので土座の時と同じように、ムシロを敷いた上に麦藁を敷いた。納戸(寝室や物の収納に利用)がある三間取りのような古いタイプの民家にはよくあるが、納戸構(ナンドガマエ)といって入口敷居が高くなっているのは、内側に敷いた藁が外にこぼれないようにした名残だといわれている。生活が豊かになると上流階級の住居と同じように板張りの民家では断熱材として畳を導入していった。 |
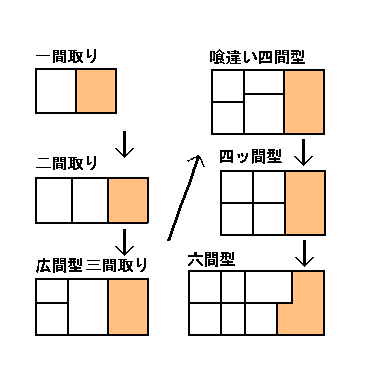 関東地方での一般的な間取りの進化 |
||
| 民家の観かた2:主屋 |